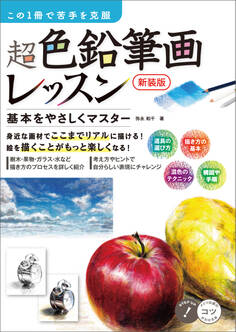※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。★ 身近な画材でここまでリアルに描ける! ★ 絵を描くことがもっと楽しくなる! ★ 樹木・果物・ガラス・水など描き方のプロセスを詳しく紹介。★ 考え方やヒントで自分らしい表現にチャレンジ◎ 道具の選び方◎ 描き方の基本◎ 混色のテクニック◎ 構図や手順・・・など◆◇◆ 著者からのコメント ◆◇◆ 本書では、単に絵を描く手順書ではなく、そんな色鉛筆だからこそできることを中心にお話を進めていきます。「手順書としてではない」ということ、そこにも色鉛筆の特性が大きく影響しています。色鉛筆とは硬い木芯に包まれた、色の芯によって着色します。そうした柔らかな毛先を持つ筆とも違う形状は、指先の微妙な力加減をダイレクトに紙へ伝えるのです。その繊細さは、力加減だけでなく描き手の個性をも如実に再現します。色鉛筆は、描き手の個性がかなり早い段階で現れ、その人の作風の独立を促すことにもなります。 そこで、本書では手順として「こうしたらできる」といった最後の一手をお伝えするのではなく、「こう考えたらできる」答えの見つけ方を集めてみました。「教えられた通りやっているのに、同じようにできない」と悩む方もいらっしゃるかもしれませんが、実はそれこそが個性であり、もしかすると誰もしていなかった新しい表現かもしれません。色鉛筆は、“絵描き"の持つ本質的な魅力に最短でたどり着ける画材のひとつともいえるのです。色鉛筆画をより深く楽しむためのヒント集として、みなさんのさらなる楽しい絵描きライフにお役立ていただければと思います。色鉛筆画家 弥永 和千◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆☆ 第1章絵を描くための心得* Lesson01 「絵を描く」とは、何をしているのかを知ろう* Lesson02観察力を鍛えよう* Lesson03自分の目的で絵を描こう・・・など全4項目◎Column 絵を楽しむ世界とは☆ 第2章色鉛筆画の道具を揃える* Lesson05色鉛筆は好きなものを選ぼう* Lesson06買ったら削ろう* Lesson07「鉛筆削り」を選ぼう・・・など全6項目◎Column 上手な水張りのコツ◎Column 「絵を描く」のに必要なこと☆ 第3章色鉛筆画の描き方の基本をマスターする* Lesson11面で塗れるようになろう* Lesson12紙を回そう* Lesson13濃く塗る・・・など全10項目◎Column 絵は何をもって完成とするか☆ 第4章色鉛筆の色を混ぜる* Lesson21色は選ばず、混ぜてみよう* Lesson22色のなりたちを知ろう* Lesson23自分の混色を手に入れよう・・・など全7項目◎Column 色は諸刃の剣◎Column 色料の3原色と光の3原色◎Column 人間の眼の不思議☆ 第5章絵を描こう* Lesson28好きなものを描こう* Lesson29構図を考えよう* Lesson30絵にタイトルをつけよう・・・など全16項目◎Column 普段からカメラを持ち歩こう◎Column 額装しよう◎Column 本物みたい! 「リアル」って何だ ☆ 第6章描き方プロセスと作例から見るコツ* Lesson44「樹木を描く」混色による色の表現、光を当てることで生まれる立体感* Lesson45「果物を描く」混色による色の表現、ものとものの関わりを描く* Lesson46「金属を描く」金属の質感表現、見えたままを描く・・・など全10項目◆◇◆ 著者プロフィール ◆◇◆弥永和千グラフィックデザイナー。2013年より林亮太氏に師事し色鉛筆画を描き始め、2015年10月色鉛筆画家として独立し活動を開始。色鉛筆だけによる絵画作品の制作を行いグループ展に多数参加。2016年2月より個展も開催。色鉛筆を気軽に絵描きが楽しめる画材として広めるべく講師活動やイベントなどを各地で行う。※本書は2017年発行の『この1冊で苦手を克服 超色鉛筆画レッスン 絵画技法の基本と応用』の書名・装丁を変更し、新たに発行したものです。
既刊(1巻 最新刊)
既刊1巻
この1冊で苦手を克服 超色鉛筆画レッスン 新装版 基本をやさしくマスター
1,900
通知管理
通知管理を見る
この1冊で苦手を克服 超色鉛筆画レッスン 新装版 基本をやさしくマスターのレビュー
まだレビューはありません。